 深夜枠で定期的に放送されていたスペシャル番組『すべらない話』―ダウンタウン・松本人志率いる宮川大輔・千原ジュニアなどの芸人たちが、聞けば必ず笑ってしまう実体験談を次々と語っていくという、シンプルながらも高い笑いのヒット率を誇る―のゴールデンタイム進出第二弾。
深夜枠で定期的に放送されていたスペシャル番組『すべらない話』―ダウンタウン・松本人志率いる宮川大輔・千原ジュニアなどの芸人たちが、聞けば必ず笑ってしまう実体験談を次々と語っていくという、シンプルながらも高い笑いのヒット率を誇る―のゴールデンタイム進出第二弾。
『すべらない話』というタイトルには本当に偽りがなくて、どの話を聞いても確実に笑わせてくれて、第8弾で初めて観た視聴歴の浅い私もこの番組は気に入っている。
“すべらない”のは、面白いネタがそろっているからというだけでなく、出演者の話術が巧みなことも理由のひとつ。例えば、今回の松ちゃんの話で、「目的地まで目と鼻の先なのに、カーナビが“高速道路に入れ”としきりに案内してきたので、従ってみたら…」というオチがミエミエのヤツがあったけれど、それでも大笑いできてしまったのは、語りのテンションを緩急自在に変化させて話を進めていったからだし。
個人的には、前々から「笑い飯」を推してたんだけど、ここ最近は劣化が激しいような…
今回のネタなんて目も当てられない。
元々ネタの練度が高いとは言えない、小学生レベルのギャグをただただ連発するだけのダブルボケコンビだけど、最初のうちはそこそこ考えたネタをぽつぽつ出してきて客の関心を惹き、徐々にネタを繰り出す速度を上げていき、最後にはダジャレとそう変わらんレベルのネタをマシンガンのごとく撃ちまくり、そのインパクトが抱腹絶倒の火力になるのが「笑い飯」の新基軸的な特徴だというのに…
一昨年から、一つのネタに新しい要素を互いに次々足していって、最終的にそのネタが完遂される段にはものすごいカオスな笑いの塊が出来上がっている、というスタンスを開拓して、本質を見誤っている気がする。
このスタンスだと、次のボケが炸裂するまで時間がかかるし、今までに積み重ねられてきたボケで笑おうとしても、慣れてしまって爆発力がなくて、全体的にイマイチな印象になってしまうので、オススメできない。
それでも、マリリン・モンローの時よりは、幾分か改良されてた気がするが。
やっぱり4年前の「奈良歴史民族博物館」のネタは神がかってたんだなぁ、と今更ながら思う。


(▲よみうりテレビサイト・実写ドラマ版『名探偵コナン』ページより)
う~ん…
放送前から期待していたスケールに比べると、少々こじまりしたものに落ち着いてしまった感が…
爆弾が出てきたのでスケールアップ感はあるけれど、爆弾ってのは「これさえあればスケールアップ感が出ます」リストの第1位と言っても過言ではないので、安直すぎて安っぽい話に感じられたし、そもそもそれだけ話がデカいブツを扱っておきながら、セットの中で話が完結してしまったのは窮屈に思えた。
大体、主人公が爆弾解体に悦に入ってて、周辺の人間の避難のことを(ストーリーが)考えないのは後味悪いって。ちょっとはフォロー入れればいいのに。もしくは、「これで失敗しても、死ぬのはあの二人だけ」ぐらいに規模を抑えておくとか。
そして、そもそもの疑問は、爆弾解体に「探偵モノ」の醍醐味ってあるんかいな?…ってこと。
爆弾以外では「探偵モノ」らしいトリックがいろいろと出てきているので、それで釣り合いが取れるのかもしれないけど、トリックのアイデアはともかく、それの演出が少々薄いところが残念。
謎の提示から、それの解決まで、あまり間(タメ)がないので、カタルシスが出てないのが問題なんだな。
それに今回ばかりは、そのトリックはオーバーテクノロジーすぎて、納得しかねる(笑)
こっちが期待してたのはさ、シリーズ最大の敵との対峙なんだから、相手が手の内を見せない不適な性格をしていることで、解決の先が見えず、もっと緊迫感があるストーリー展開になってる、ってことだったんだけど、割とあっさりとした軽めの描写に抑えられたね。
そして、トリックよりもこっちの方がキモかもしれない「二人の恋の行方」だけど(笑)、「女の論理」ってのが振りかざされてる気がして、ちょっと疑問。
相手への思いやりの気持ちから派生してるとはいえ、「どうせアンタはそういう風に思ってるんでしょ?」と勝手に思って去ってしまうのは、ただ一人で勘違いして迷走してるんだったら可愛いんだけど、相手を目の前にしてロクに話も聞かずに自分の勝手な想像をゴリ押しして決め付けて、相手が正直に「前はそう思ってたときもあった」と枕詞代わりにポロッと漏らしたら、「そら見なさい、やっぱりね」と自分の正当性を勝手に強調する発言をして、そのまま女側優位のまま別れ別れになってしまうので、「ちょっとは男の話を聞いてやれよ」ってな具合でイヤな感じがしたなぁ…
なんかヒステリックみたいで。
んでもって、ここでの一番のイヤな感じは、「二人の仲がそれほど良くなかった時期だったために、勝手に早とちりしてしまった」という流れでもないのに、上記の話にもつれ込んでいることで、ラストでの和解による感動を狙って、状況が急性に仕立て上げられたという「ストーリーの都合」がありありと主張されてることなんだよな。
…でもまぁ、主な視聴者は女性だろうから、女側の気持ちを優先したこの流れの方が、視聴者的にはいいのかもしれんが。
…などなどと不満を述べてきたが、実は、それほど「つまらない」と感じたわけではない。
今日の話のみならず、このドラマシリーズは「あまり話の質的な深度が深くなく、安直なときもあり、時折安っぽささえある」という軽い作風を磐石な基盤として成立させていて、しかしその基盤のアベレージをできうる限り高い位置に置くことが心がけられ、そのアベレージは下がることがなく、むしろ基盤の上に足されている部分が面白く感じられて、魅力になっている。
軽い作風・高いアベレージというのは今回も維持されていて、その部分への期待には応えられていて、良かった。尺が長くなった分に足された量がイマイチだっただけ。
商業的にはともかく、作品的には凡打だったかもしれないけど、『ジョシデカ』みたいな三球三振や低い内野フライみたいなのではなく、ちゃんとヒットになっているのだから、その点は評価したいな。
この勢いで、来年の映画を作っていただけると、とても安心な気がする。
楽しめる出来にするのは、上記の不満が解決されるべきだけどさ。
そんな感じで、今日で終わりなのが残念だよ、『ガリレオ』は。


(▲フジテレビサイト・『ガリレオ』ページより)
えっ、実写版『コナン』?
ナニ ソレ オイシイ ノ?
そして使われていたBGMの半分は『ゴジラvsスペースゴジラ』のサウンドトラック。
普段の放送でも時々使われることもあるし、そう意外ではないけれど、やっぱこういう場で聞くと顔が緩んでしまう。
そして、音楽が画面にマッチしてるのを見るほど、「これって、映画向きの音楽じゃねぇよ、服部隆之」と思ってしまう(笑)
でも『ゴジラ2000』のときは退屈だったから、ケレン味ばっかりのこっちの方が好きなんだよ。
CD欲しいなぁ~
番組の内容に関しては、「いつも『どうぶつ奇想天外』見てたら、驚き情報でも何でもねぇよ」というのばかりだったけど(ってか、最近のは特にそう)、常に年少の視聴者が新規にやってくる番組だから、こういう基本情報を教えて将来の良き理科マニアの養成を行なう必要があるんだよね。
『ジョシデカ』出演者がゲスト解答者として来てたけど、宣伝必死だな、不人気(笑)
2話で切っちゃったけど、今どういう話になってるんだろうなぁ…
「名探偵コナン」声優と原作者が離婚
人気アニメ「名探偵コナン」(日本テレビ系、月曜後7・00)のコナン役で知られる声優の高山みなみ(43)と、同作品の原作者で漫画家の青山剛昌氏(44)が離婚していたことが9日、分かった。
2人は05年5月に結婚。しかし、青山氏は締め切りが近づくと仕事場に“缶詰め”になることが多く、売れっ子声優の高山も多忙を極めた。すれ違いの生活が続き、溝を埋めるのが難しい状況になった。青山氏はスポニチ本紙の取材に対し「コメントはできません」としている。
2人は、10年ほど前に青山氏原作のアニメ「YAIBA」の収録で出会った。04年1月ごろから交際に発展、翌05年3月に高山が青山氏に逆プロポーズ。結婚が報道された際には「コナンが結んだ縁」と話題になった。
高山はコナン役のほか、宮崎駿監督の映画「魔女の宅急便」の主人公キキなども務めた人気声優。シングルもリリースするなど元祖アイドル声優の1人として活躍した。青山氏は高額納税者番付の上位常連で、05年には1億3831万円を納税。「名探偵コナン」は94年から「週刊少年サンデー」に連載され、単行本が1億部を超える大ベストセラーとなっている。
スポニチ[ 2007年12月10日付 紙面記事 ]
ま、結婚のときもここに載せたので、今回も一応。
それはともかく、『ガリレオ』や溜まりまくってた『ジョシデカ』観てたら、『相棒』の画面作りって「凝ってるなぁ~」って感じる。
普通のドラマの場合、セット内撮影だろうがオープンだろうが、どの瞬間でもカメラ位置がアイレベルばかりで固定されてて、演劇的な平板な画になりがち。
(まぁ、それは予算の関係で使える機材が限られてるということも関連してるが)
それと比べると『相棒』は、長回しのトラッキングショットとか、奥行きを利用した前景遠景を往復する芝居とか、イコン的な小道具やレイアウトの使い方とか、様々な映画技法がいろいろと使われていて、どの瞬間でも魅力的な画作りがなされる。そして場面演出として的確だから観ていて快いのが良い。
さすがは天下の東映。伊達に老舗じゃない。
全部のドラマがこの水準でやってくれればなぁ、という夢想が尽きないヨ。


見る気はなかったのに、賑やかしにテレビ点けて8チャンネル流していたので、観てしまった。
東野圭吾原作なのか。
福田靖脚本らしい、人間ドラマ性よりも事件性重視のお話。
奇想天外・摩訶不思議な事件(1話では人体発火)が、科学の理論に基づいたトリックが使われて起こり、それを科学バカの変人教授の知恵を借りて、新米女刑事が説いていくというのが、この作品のミソ。
「奇抜なアイディアの新機軸ドラマ」と宣伝されていたが、それは『銀狼怪奇ファイル』や『TRICK』がすでに通った道だ。
まぁ、奇をてらった体裁だったそれらに比べて、一般向けに適した真面目で普通の仕上がりになっているのが、いかにもフジテレビ製、って感じだけど。
そして、これは原作者の力量の話になるけど、サイトレーザーと不可視メーザーの違いを活かしたトリックと謎説きや、大気の状態で進行方向が容易に変わって安定しないというメーザーの特性を利用した犯人の性格付けは、なかなかに面白い。
(また後で加筆します)
さてさて、新番組ラッシュの時期がやってまいりました。チェックが大変なんだよなぁ…
とりあえず、アニメで注目したいのは、原作読んだことがある『スケッチブック』に、アフタヌーン連載原作の『もっけ』と『しおんの王』にプラス『もやしもん』。
京アニ制作の『CLANNAD -クラナド-』は地上波でやる縁でとりあえずチェックしときたいし、監督:水島精二×脚本:黒田洋介の『機動戦士ガンダム00(ダブルオー)』は実制作のブレインスタッフ的に結構期待、新房マジック影響下になるだろう『ef -a tale of memories-』は「どないな風に仕上がるん?」感があるから見てみたい気が…
『D.C.Ⅱ』はザッピングしてちょこっと見たけど「いきなりカップル成立」以外は無難な仕上がりぽくてビミョー、『灼眼のシャナⅡ』は前作からの誼だけど、前作にそれほど惹かれてたわけではないのでどうすべか…
前評判とあらすじ読んで見てみようかな、という気になったのは『BAMBOO BLADE』と『BLUE DROP』。『ドラゴノーツ』もある意味気になる(笑) あと、『プリズムアーク』がどれほど大張アニメしてるのかも。
実写では『ULTRASEVEN X』。『ネクサス』路線をさらに押し進めたような感じなので、見る前から失敗臭が漂っている(笑) 『ネクサス』は2クールかけて何とか挽回したくさいけど、今回は1クールだからだいぶ厳しいんでないの?
川北監督が浦沢義男の脚本で作ってる『Kawaii! JeNny』は、かなりぶっ飛んでるので、ちいと見てみたいけど、関東限定なのが惜しい!(笑) でも、やっぱりビーム合戦ですかい(笑)
『相棒』の再放送が面白かったので、今期から生視聴してみようかと思ってるんだけど、今度は第7期。そろそろネタ的に行き詰ってくる時期だと思うので、ほぼ初体験の私がこっから見てどうなるか…
土曜ワイド劇場版か第1期のビデオ借りてきて、劣化してるかどうか比較しようかしら?
“『あぶない刑事』の女性版”との売り文句で注目しているのは、『ジョシデカ!』。『ハプニング大賞』の映像でチラ見した限りでは、暴走する気はなさそうで残念。泉ピン子と仲間由紀恵のキャスティングがどんな風に転ぶのか…
そして『金八先生』が控えていますよ。原作者・小山内美江子が企画会議に関わっていない初めてシリーズにして、金八定年による最終シーズンの可能性もある今期。植木Pも福澤Dも参加しない。いろんな意味で注目です。
室井
「警視庁の室井だ。慌てずによく聞くんだ。今日警視庁が所轄署の管轄エリア統合に関する条例改正案を提出した。それだけじゃない。これによって新たに『湾岸署』が実際に設置されることになりそうだ。正式に決定すれば、ファンサイトでも大きな話題になるはずだ。その中の一部は世間の人気にかこつけた安易な決定だと言ってに反発する、と踏んでいる。絶対に揉め事を起こすな」
青島
「…もう起きそうです」
室井
「なに?」
青島
「あのぉ、フジテレビが、『湾岸署』はもう商標登録しといたのでそこんとこヨロシク、と言っています」
室井
「……。」
「湾岸署」が来春現実に…警視庁「湾岸署」誕生へ=都議会に改正案提出
警視庁は27日、9月定例都議会に、来年3月に東京・臨海地区に開署予定の警察署の名称について、「東京湾岸署」とする条例改正案を提出する方針を明らかにした。
現在、東京水上署が管轄する品川、大井ふ頭、お台場地区に加え、深川署内の辰巳、東雲地区、城東署内の夢の島、新木場地区を統合して管轄する。これに伴い、東京水上署は廃止する。
設置場所は江東区青海で、23区内では最も広い面積をカバーする。建物は地下1階、地上9階建て鉄筋コンクリート造になるという。
6月27日18時0分配信[時事通信]
お粗末さまでした。
(ナレーターが大友龍三郎に替わってたね)
そんなテイタラクの中、興味をそそられたのは“トリビアの種”の「学者が考える人類史上最も“カワイイ”キャラクター」。
ちなみに、四方田犬彦に言わせれば、「かわいい」という概念は日本以外には存在しない、ないし、西洋では発見されなかったものだそうで、ここでの「人類史上」ってのはつまり「日本史上」と同意なわけだ。
看板の割に、なんかやろうとすることが狭い気が…
(でも最近では、アメリカ等にも「kawaii」が上陸して、徐々にワールドワイド的になっとるようですが)
(※英語で「かわいい」と翻訳できるものはあるけれど、cuteとかcharmingだと「ガキっぽい」って否定的な意味の含みがあるし、darlingは愛の深さが強烈過ぎる。適度な距離をとって肯定的な意味で使ってるのは日本だけ)
さらに付け加えると、「かわいい」と「美しい」を比較すると、「美しい」ってのは高嶺の花を恋焦がれるようなものだけど、「かわいい」はもっと距離が近くて、手元に置いておきたいぐらいの好きさ加減なのよね。
それに「美しい」が完全無欠の絶対的な対象に対する畏怖の感情が含まれているのに対して、「かわいい」は何か欠けているものに対する愛おしさというか同情ないし優越感を表しているという。
(だから私は「萌え」は「かわいい」の感情を大本にした言葉だと思うけどね。オタクがマンガやアニメのキャラクターに「萌え萌え」言っちゃうのって、マンガやアニメのキャラクターが抽象的に簡略化された線で描かれた欠けた存在だからだし、それに、男オタクから萌えキャラと呼ばれるキャラクターを見回してみれば、何か人間として大事な部分が欠けているような頭の足りない連中ばっかりだし(笑) あと、「赤松健って萌え作家だよねー」という文章をよく見かけるけど、正確には「萌えとエロの人」だから。「かわいい」と「エロ」はリビドーの原点が違うんだってばッ!!)
あと、かわいさの背景には必ず「グロテスク」という概念が存在している。
冷静にかわいいものを見てみると、実は結構グロテスク。昔、『たけしの万物創世記』でやってたけど、『おジャ魔女どれみ』のキャラデザをそのまま実写の赤ちゃんで再現してみたらどうなるか、というのをCG使ってやったら、目が異様にデカくて気持ち悪く、異生物っぷりが感じられた。


 (←再現)
(←再現)「かわいい」と「グロテスク」は紙一重ということで。


ほれ、トリビアで作られたのだって、気持ち悪い気持ち悪い(笑)
さらにさらについでに、「かわいい」と「ノスタルジー」も似たようなもので、時に「ノスタルジー」もグロテスク化してしまう。ノスタルジーがグロテスク化というか恐怖や脅威になってしまうというのは、漫画の『20世紀少年』や、『クレしん』の『オトナ帝国の逆襲』でも提示されていたし。
閑話休題。
生物学的に「かわいい」を科学すると、「かわいい」という感情は、基本的に赤ちゃんに対する親の“種の保存本能(「子どもなら守るべし!」)”から来るらしいので、学者先生らが挙げた、心理学的面から見た「かわいい」というのは、大人が子どもを見る視線に由来しているのよね。
体が小さい(=頭がでかい)、丸っこい、額が大きい、目が大きくて離れていて顔の真ん中より下についている、強さがない、動物的で人格が薄く見てる側が感情移入しやすい、単純なデザインで欠如感がある、暖色系(=人間の肌の色)が好まれる…等々、すべて子どもに当てはまる要素だと言える。
…でもね、世間から「カワイイー!」と言われてるキャラクターにもかかわらず、上記の条件に当てはまらない項目が多い例外的なキャラクターがいることを、真っ先に思いついた。
ドラえもんだ。
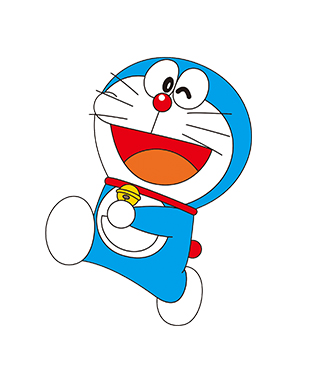
目は頭部の上の方に付いてるし、完全な寄り目で、体色は青ベース。上の要素の半分が否定されているではないか。
おまけに、ドラえもんって役割が保護者的で、読者や視聴者に対して優越的なんだし。
それでも皆さん「かわいいー!」というし、緒方拳もハマってる(笑)
頭でっかちとか目の部分がでかいとか、そこらへんの要素がかわいらしさなのかもしれん。
…まぁ、こんなことを思うのも、夏目房之介がそう言ってたからだけど。
相変わらず、高得点が出過ぎ、という不満要素が存在する「仮装大賞」ですが、ちょっと擁護的な考えをすると……回数を重ねると参加者の顔ぶれも大体似たような感じになってきて、そうした歴戦の勇者たちが経験を生かして、ウケが良いものを分析したり、より高いレベルの表現やアイデアを出してきたりすることで、ほとんどの出場者が合格になる域にまで達したのかなぁ、とか思ったり。
ただ、ウケがいいとか高度な表現に必要だからって、子どもを大量に動員して、凝った仮装を次から次に繰り出していくというタイプの作品が私はどうも嫌いでねぇ…
なんか、数こそ勝利、みたいな感じになってるのが卑怯だと感じられることが多いんだよね。
今回の「孫悟空」もいろいろなアングルやショットサイズで“撮影”してる感を出すために、二十人以上が参加している大所帯の作品だけど、アイデアが人数ありきの普通のものでそれ以上のものを感じなかったので、あまり評価したくない。
“撮影”を意識した「僕の彼女が怒る理由〈ワケ〉」も、同じ感じで人数使ってるけど、こちらはフィルムの撮影速度に着目して、『マトリックス』的な瞬間スローを使っているところが新鮮だったし、高速逆回しを活かす脚本面的な構成も面白くて、評価は出来る。
ただ、撮影技術に着目した作品は、如何せん最近出過ぎている上に、ギミックが凝りすぎているので見た後に疲れる、という欠点があるにはある。
そう考えると、最優秀賞の「池に映る風景」は、雰囲気だけを重視したシンプルなアイデアに、シンプルだけどインパクトのあるギミックを使っていた、そのさじ加減が素晴らしかったなぁ~
「暑~い!」は、子どもを使った卑怯な作品の部類に入るかもしれないけど、「体を引き裂いて中から別の人間登場」というスプラッタ寸前のアイデアは「うわー! こんなん見せちゃっていいのー!?」という面白味があったし、どういうギミックかよく分からないものの、シンプルでインパクトがあるものだし、子どもをオチに使わないとできないネタを考え出したということでも評価できるかもしれない。
何にしても、帽子の中にすっぽり収まっちゃった女の子、可愛いねぇ~(笑)
子どもを使って卑怯だったのは「ウルトラマン」。私には、仮装大賞の舞台で、父子がちょっと豪勢にウルトラマンごっこをしてるだけにしか見えないかった。
「チョキチョキダンス」も人数合わせ系に入るかもしれないけど、音楽に合わせてチームワークの取れたダンスを披露していて綺麗だったので、まぁよし。
ただ、踊りと音楽で誤魔化しているような感じがするので、評価はしないけど。
撮影技術のほかに、最近では脚本的な面で工夫を凝らしてるのも多くて、技術賞を取った「そしてグチャグチャになった」も、バスター・キートン的な不幸の連鎖を考えて作られている脚本系。
で、ちょっと話を戻すけど、人数ありきのネタが個人的に嫌いということがあって、独りで虚しくがんばる小ネタ集的な作品が、私は大好きだったりする。
なんかねー、ネタが次々と繰り出されるという大盤振る舞い感が楽しいんだよね。「それも数がモノを言ってるじゃねぇか」なんて批判もあるかもしれないけれど、個人的にネタの数が多いのは気にならんらしい。あと、独りでやるという哀愁漂う姿が何とも愛しくてねぇ(笑)
「いろんなリン」は、もう、理想の独人小ネタ集。
「メタボリックジャパン」は、自虐っぷりと白けっぽさが、もう、笑うしかないよなぁ~
「サンダーバード」は卑怯だよなぁー。
ジェットエンジンの噴煙をすすり食う麺に見立てて、延々と「揖保の糸」をすすり続ける、というただそれだけのネタなのに、糸につるされて際限なく徐々に上に上がっていく、という小技を合わせることで、単調さを別のものに変えてしまっていたのが、小憎たらしい。
あんまりにもしつこく繰り返されて続けられると、「引き延ばし効果」になってしまって、マヌケ図に見えてくるんだよね。
おまけに笑えるまでにオーバーに見開いた眼で延々とカメラを凝視しっぱなしなので、笑えて笑えてしょーがないのだもの。
「このアイデアは捻りが無くて繰り返しで時間を稼いでるつまらない部類のものだぞ」と頭で理解していても、映像で見せられるとどうしても笑ってしまう。等速で上昇し続けるってのが、ポイントだよね。
「ど根性大根」、外人をひたすら虐めぬく、という反国際化社会的なヤバイ図が展開されていたので、もう、笑うしかなかった。
欽ちゃんとのトークでも「ダイジョーブ!」とにこやかに答えていたし、強いなーこの人。
笑点メンバーの黄色いバカ、木久蔵師匠の新しい芸名がこのたび決定した。
実子の林家きくおが落語家の真打に昇進するにあたって、「木久蔵」の名前を譲るという話なのだが、そうなると譲った後の木久蔵師匠がどういう芸名を名乗るのかが問題になる。
たいていの場合は、自分で作ってしまうか、師匠に考えていただくのだが、木久蔵師匠はそんじょそこらのマジメな落語家とは一味違う。
前代未聞の「公募方式」で決めるという。
伝統を重んじる落語界では、なんとも型破りなやり方である。
でも、公募にしたのは、新しい名前を考える頭が足りないのか(笑)、襲名披露で沸かせようという計算を働かせた策士なのか…
で、決まった新しい名前なのだが、“木久蔵”改め、「木久翁(きくおう)」になるという。
おバカキャラで売っている木久蔵師匠にしては仰々しい名前とも言えるけど、『笑点』で数十年も慣れ親しみ浸透してきたので、“木久蔵”という名前の響きと木久蔵師匠のキャラは不可分のような気がして、だから、あまりにも違った名前になるよりは、「木久ちゃん、木久ちゃん」と親しみを込めて呼べる“木久蔵”の響きが残っている芸名の方が、ホッとできたり。
ただ、どうでもいい事柄だけど、ちょっと思うことは…
林家きくおが木久蔵になって、林家木久蔵がきくおうになる、というのは…
それ、ちょっと間違うと、親子で名前を入れ替えただけ、ってことになりかねんのではないか!?
| 10 | 2025/11 | 12 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |

