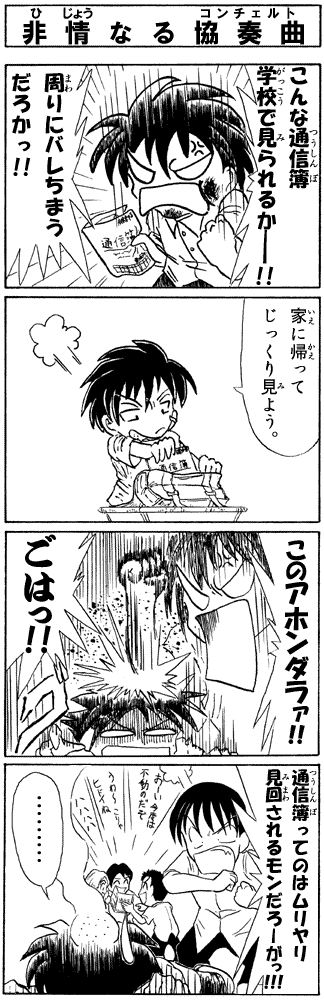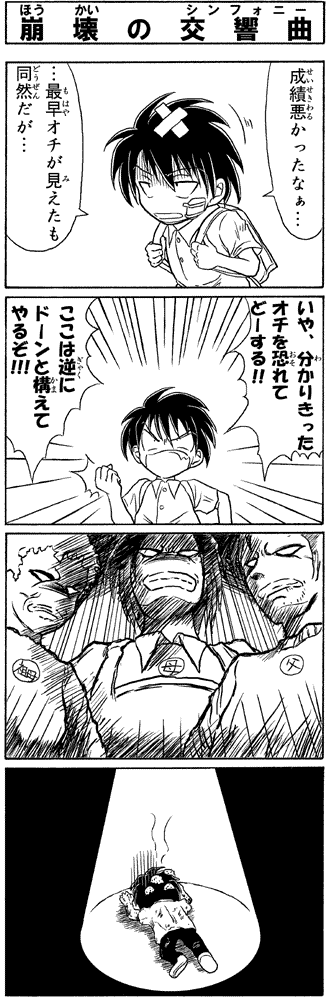懸念事項が現実のものに…
オレ様千秋改心の布石になぜか使われるアニメ登場の回。
まさか月9で釘宮理恵の声を聞けるとは思わなんだ。
やっぱり実写とアニメをドラマ上でリンクさせるのはキビしいものがあるなぁ…
例えば上の「助けるために手を握るシーン」は、マンガだったら、本編もアニメ部も、同じ“線で描かれたもの”なので、画的な互換性があって、シリアスなシーンでもドラマ的な結び付きが見ている方にすんなり受け入れられるけど、実写とアニメだと画ヅラが質的に違うので、違和感が先行して、シリアスなシーンならではの感動に至らない気が…
あと、千明の性格からすると、「アニメなんてマトモに観てられるか!」という気持ちの方が強いと思うので、呆れた顔しつつもなんか観続けてる、という演技を個人的には期待していたし、もしくはアニメが流れている間は千明のリアクションを映さない(玉木宏を長時間映さないなんて、そんなッ!)、というのが手だと思っていたのだけれど…
割とハマっとりますな。
後半(右2枚)なんて、わざわざ姿勢正して観てるし。
アニメの手を掴むシーンの前に、没頭してる千明の姿をカットインさせたのは良いと思うのだけど。
あと、俳優の演技…というか発声の悪さがギャグシーンの足を引っ張っていることが顕著になってきた。
ちなみに、劇中アニメのスタッフをエンドクレジットで調べてみると…
「プリごろ太 宇宙の友情大冒険」
声の出演
ごろ太 工藤晴香
プリリン 川上とも子
カズオ 芝原チヤコ
リオナ 釘宮理恵
マイケル 大山鎬則
宇宙船 小野涼子
アニメーション監督・脚本・絵コンテ
カサヰケンイチ
演出・作画監督
音地正行
アニメーション制作
GENCO/J.C.STAFF
映像提供
のだめカンタービレ アニメ制作委員会
J.Cかよ。意外と豪華だな。
とあるUHF系テレビ局の某深夜アニメでの一コマ…
こんな切れ方するキャベツなんてねぇよっ!
…というのは、もう古いネタだな。
深夜アニメは作画崩れがよく起こるから、まぁ仕方あるまい。
…が、キー局のゴールデン背負ってる作品で作画崩れが起きたら、「仕方あるまい」では済まないだろうな。
…じゃあ、今日の『名探偵コナン』はどうしてくれよう(汗)
1954年11月3日。
『ゴジラ』第1作の公開第1日目である。
というわけで今日はゴジラの誕生日。
坂野義光監督の『ゴジラ3D』も頓挫しちゃったみたいだし、帰って来るのはいつになるのやら。
そして何の因果か、関西学院大学で自主制作特撮を観てましたよ。
監督は等身特撮ヒーロー番組のセオリーをよく分析していらっしゃる。
結果に反映されているかどうかは言わないが。
詳しくは過去の日記を参照のこと。
もう、どこが『踊る大捜査線』なんだ!?、と原形を留めないまでに変形したスピンオフドラマ。
…などと文句を垂れつつも観てしまうから、制作者側をつけ上がらせちゃうんだろうな。
先週『容疑者室井真次』を観て、そのあまりに小物の悪役然としたキャラクターを知った時には、「え~~っ!!? こんなの主人公にしてどうやってドラマ一本でっち上げるんだよ!!?」と驚いて、呆れてしまいました。
感情移入の対象になりえないキャラを主人公に立てると、ドラマとして立ち行かなくなると思うのですが。
これを回避するために考えられる方法は二つ。
灰島には主人公ではなくピエロ役を演じさせ、周辺人物に主視点を置き、灰島が事件を掻き乱すせいで翻弄させる周辺人物たちにドラマを求め、最後には灰島が負けて良かった良かった、という話にする。
灰島に挫折を味わわせることで葛藤のドラマを噴出させ、改心させることで灰島を感情移入可能なキャラクターに変貌させて物語を進行する。
今回は無難に後者を選びましたな。
でも、君塚良一が脚本書いてるくせに、エピソードの配分バランスが心地良くなかったり、提示された問題が足並み揃わずにラストに向かって進行していたり、いまいちうまくいっていない。
最後の最後には、折角改心させた灰島を完全に悪役に戻してしまうし。
(基本悪モノだけどちょっとは改心したんだぜ、みたいな描写が出てくる期待も打ち砕いてくれたからなぁ)
多分、キャラクターの同一性が維持させるように話を調節するのを重視するあまり、バランスが崩れてしまったんだろうな、とは思う。キャラ重視の『踊る』では、こういう処理のが大変だから。
ただ、灰島を改心させるイベントの配置は面白い点が多く、「あの状況から改心させるために、よくこんな巧い舞台設定を考えるよなぁ」とは感心した。
…が、もう『踊る』の出涸らしすら限界です。