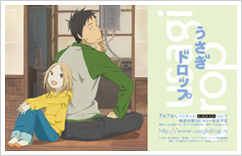 1話アバンの、水彩画チックなボヤけた影の付け方をした特殊な仕上げと、PUFFYの歌と「みんなのうた」チックな簡略の行き過ぎた記号アートなアニメーションで、最初「NHKアニメ!?」と思ったりした(笑)
1話アバンの、水彩画チックなボヤけた影の付け方をした特殊な仕上げと、PUFFYの歌と「みんなのうた」チックな簡略の行き過ぎた記号アートなアニメーションで、最初「NHKアニメ!?」と思ったりした(笑)
松ケン・芦田愛菜主演で実写映画が公開されるのに合わせて、『ハチミツとクローバー』・『のだめカンタービレ』みたく宣伝兼ねてアニメ版も放送しよう、という企画で作られたであろう、実にフジテレビ・ノイタミナ的発信なアニメ。
ちなみに、関西は「ノイタミナ」という枠ではなく、「アニメわ~く」という枠名称になっている。
制作しているのはプロダクションI.G.で、日常ドラマ系アニメをI.G.が手掛けるのは意外な気がする。
…って、調べてみたら、『君も届け』もここでしたね(汗)
爺さんの隠し子という身寄りのない幼女を、冴えない30歳独身男性が引き取って、慣れない子育てに奮闘するという、よくある設定の疑似家族モノ。
「爺さんの隠し子」の衝撃性以外は、物語の前提設定はよくある感じなのだが、よくある設定というには中身がちょっと異質な気がする。
子育て奮闘モノに、というか、この手の日常リアクションが大事な作品には当然あるべきであろう“衝突”がない。
たとえば、育てる側の方が、子育てを甘く考えていて失敗したり、「この子は一体何を考えているんだ、さっぱり分からない!」とか子に理不尽な怒りを覚えたり、仕事と子育てどっちを優先させるのか悩む場面に突き当たったり、子どもの方は「(おじさんは、私のこと分かってくれない)」みたいな事を言う…いや言葉には出さずに行動だけなんか変になっていたり、とか…
登場人物同士の考えや思いのズレ、理想と現状のズレが発生して、そのズレの不満を他の人にぶちまけて“衝突”したり、葛藤の末打破しようと突き進んでいく“衝突”が起こってドラマが進んでいく、というのが普通のTVドラマとかの作劇だと思うが、この作品にはそれがない。
りんが悩んでいる理由をすぐに察して解決したり、仕事もほとんど迷いなくスパッと変えたり、あるいは、葬式の場で親類に無下にされても不満を発露させることなかったり、託児所でも不満を感じなかったり…
大吉もりんもいい子すぎます。
とはいえ、この作品見てる分には、それがとっても心地よかったりするんですが。
1話終盤~2話前半の、年下の叔母さんネタを活かしたやり取りはちょっと好み。
現実的かどうかで言ったら、葬式でやたら暴れまくってたウザい親類の麗菜とか、「りんちゃん、それ壊さないでね。バイバーイ」と仲良さげながら自分の都合を押し付けて帰ってく託児所の子みたいに、我を目一杯主張する子どもの方が、現実的。
劇中にそういう人物が的確に描かれているということは、制作側に描く能力がないのではなく、メイン二人のキャラクター設計をわざわざそういう風にしているということで、ここら辺突いても詮無いことではある。
3話目で、りんの本当の母親の情報が入ってきて、ようやく衝突要素が発生してきた感じではある。
「激闘!善と悪2台のナイト2000」
(原題“TRUST DOESN'T RUST”…訳すと、「絆は傷つかない」)
この話はいわゆる“ニセ主人公モノ”。
『ウルトラマン』とか『仮面ライダー』でよく見られる、悪人がヒーローと同じ力で対抗すべく・あるいはヒーローを陥れるために、そっくりのニセモノを作って戦わせたり悪事を働かせたりするヤツだ。
ニセモノの方は、体のどこかが不自然に尖っていたり色違いだったりして、視聴者には判別が簡単だったりするのも、お約束。
『ナイトライダー』の場合、主人公マイケルのニセモノが現れる話も後々あるのだが、今話はキットのニセモノ。
俳優のニセモノが存在するというのを撮るのは結構手間がいるが、キットの場合、被写体が車だから、そこら辺簡単。
『ナイトライダー・コンプリートボックス』を読んでみると、初期はキットの撮影用に使う改造トランザムの台数が少なかったというが、それでも3台はあったというから、ここから「予備車あるんだから、コイツを利用できる話でも作ろう」というアイデアが出てくるのは、当然のコトなのかもしれない。
ニセモノが出てくる話というのは、どういう作品でも大概面白く仕上がってきて、『ナイトライダー』でも例外ではないので、日本放送版で2時間スペシャル以外に日曜洋画劇場版の作品として選ばれたのも納得というもの。
ここで登場するキットのニセモノの名はカール。
キットより先に制作されキットと同等の能力を持つが、自己防衛を優先させるプログラムが災いし凶暴で手が付けられなかったので、博物館に廃棄されていたのが、コソ泥たちの手違いで蘇ってしまった、という設定だ。
『ナイトライダー』ファンの間でも、コイツの人気は高い。
ちなみに、キットが"Knight Industry Two Thousand(ナイト産業社製2000版)"の略なのに対し、カールは"Knight Automated Roving Robot(ナイト社製自動行動マシン)"の略だ。
この話のカールは、“悪のナイト2000”というより、無邪気な暴れん坊のような感じ。
もっというと、アホの子っぽい(笑)
ただのスピーカー付人形を勝手に敵認定して、体当たりでぶっ壊して「フハハ、原始的な機械め」と勝ち誇るとか、よく知りもしなかったブタ箱の意味を性急に理解して「それイヤ」と一目散に逃亡とか、サーキットの修理について駄々こねるとか、ラストもいくらでも避けようがあるのに正面衝突の危機にわざわざ危ない崖方向に向かって避けていくとか、頭のネジが一本抜けているというか、電子頭脳の回路がどこか抜けてる気がする。
ちなみに、カール再登場の「悪魔のナイト2000カールまたまた出現!復讐の空中大勝負!!」では、カールが悪知恵で一般人を悪事に唆していて、副題どおりの悪魔っぷりを披露してくれている。
そして、そっちの話は「キットが悪意を持ったらどうなるか」というシミュレーション・エピソードになっているのだが、今話は「キットを悪人が使ったらどうなるか」というIFを膨らました部分がメインである。
実際ナイト2000を悪用したら、ガワが硬いからどんな壁もブチ抜くし防御最強、悪路や袋小路もジャンプで飛び越すし、しかもA.I.搭載してるから労せず手数が一つ増えたような形になって、お手軽に犯罪し放題だからなぁ
そして、悪事に利用する方も、最初は小金目的の小さな欲望を叶えていたのが、悪事の規模がどんどん肥大化していって、遂には仲間割れ、そしてカールに裏切られて破滅、とこれまたこの手のお話のお約束を行っている。
ニセモノが登場する回では「これが無いと意味ないだろ」という、ニセモノの悪行についてホンモノの方が疑われたり被害受けたりとばっちりを食うシチュエーションは、この話の中でもちゃんとある。
ただし、CM明けでいつの間にか容疑晴れててそれ以後「このままじゃ、またオレたちの方が疑われちまう」みたいな話題やシチュエーションにならないので、エピソードのつっこみ具合として物足りない感じではあるけど。
警官に「ニセモノと区別するために、色を塗り替えては」とアドバイスされてるけど、キット自身が「私はこの黒が気に入っているのです。」と発言。やはり黒のボディカラーには強い思い入れがあるようだ。
ちなみにカールは、再登場回ではツートーンカラーに塗り分けているので、ボディカラーについては頓着していない模様。
キットとカールの決着は、切り札として取り付けられたレーザーが決定打にならなかったせいで、ある意味煮え切らない形に終わっている感じ。
キットが正面衝突コースにいるのが前から分かっているのに、直前で避けようとしてハンドル操作誤ったら崖から落ちてドカーンで終了、って、「同等の力を持っているせいでキットでも倒せない敵との対決」というテーマの話にしては、直接のガチンコ勝負なしの結果なんて安易すぎませんかね?
分子結合核を持っているナイト2000が崖から落ちた程度でぶっ壊れた挙句爆発するのかというところもあるし。(実際、2年後大した損傷もなく復活する。)
まぁ、機械である己を信じるカールと、人を信じる(人が運転する)キットとの対決の決着を寓意的に付けるとすると、これがベターなアイデアなのかもしれないが。
本国放送順では、ボニーが実働面で活躍する初めてのエピソードと言っていい。
途中さらわれて囚われのヒロイン的な形になるし、カールとの対決時もキットから降りることなくマイケルと共に立ち向かうし、カールを討った後は吊り橋効果で危うく(笑)マイケルといい仲になりかけてしまう(ま、3秒程度ね;笑)
★本国放送版&原語と日本放送版&吹き替えの違い
本国順ではこのエピソードで初めてキットがレーザー兵器を搭載するが、日本放送版では先にシーズン2の初回スペシャルを放送してしまっていて、そこですでにレーザーを使ってしまっているので、吹き替えは「レーザーを以前よりパワーアップさせた」としてある。
この後のシーンで、ボニーから「レーザーは2発しか撃てない」と注釈が入るが、日本放送版ではカットされていて、カールに対して2発目のレーザーを撃った後、「今のが最後のレーザー!」とボニーのセリフを入れて説明する流れになっている。
日本放送版見慣れた人にとっては、キットのボイスインジケーターというと3連パーグラフであり、カールがそれのアレンジバージョンみたいな感じになっているが、実は、3連パーグラフのボイスインジケーターは本国版ではカールのものの方が先。この時分のキットのボイスインジケーターは、まだ赤の四角ランプがパカパカ光るタイプのものだった。意外とカールの方がおしゃれなデザイン。
…の割に、カールのボイスインジケーターが映るカットは、ボイスインジケーターの部分だけ作って、テーブルの上にそれだけをちょこんと置いて撮影した「もうちょっとリキ入れて作れや」と言いたくなるレベルのものだが(汗)
日本放送版では、「重戦車砲撃網大突破」の話から直結しているので、冒頭のキットがマイケルの女性遍歴について語るシーンには、ロビン・ラッド中尉の名前がアフレコで足されている。
そして原語では、マイケルが「(複数の女性とのお付き合いは)友達の輪を広げてるの」と言ったことにキットが「友達なら私がいるから十分でしょ」と反応していてキットが意地らしくて愛らしい感じなのだが、日本語アフレコでは「じゃあどうしてその友達同士で(痴話)ケンカになるんですかね?」と意地悪く答えていて可笑しい。
そーいえば、「重戦車砲撃網大突破」ラストも、原語では、巻き込まれ型の事件介入で使ったお金を経費として認めてくれとマイケルが嘆願するシーンだったのに、日本語アフレコではデボンがマイケルをナイト博物館視察に引っ張っていく内容にアレンジされていたなぁ。
そしてラストのキットのセリフ。字幕では、(同類が居なくなっても)「天涯孤独、それが私の運命」と現状を肯定して話が終わるのだが、吹き替えは「本当を言えばマイケル、すごく寂しい気分です」と一歩進んだ解釈でアフレコしている。
「決死の替え玉作戦!ナイト2000凶悪武装軍団マル秘計画を暴け!! 」
(原題“INSIDE OUT”…訳すと、「反転」)
なかなか証拠を掴ませないキンケード大佐率いる犯罪シンジケート集団に、その組織に雇われた人間・デューガンだと偽ったマイケルが潜入、突破口を掴もうとする話。
副題の英語原題は「INSIDE OUT」は「さかさま」という意味だが、今話の趣旨をよく踏まえているサブタイトルだと思う。
マイケルがデューガンと入れ替わるし、マイケルが探っていた大佐の目論見も途中で別のものと入れ替えだと判明し、そもそも大佐の行動を阻止するために動いていたのに終盤は大佐の行動の手助けをしなければならない羽目になり、ラスト刑務所で外から来るを待っていたデボンは内側に入ってきたキットとトラックを見て…という感じで、逆転逆転の話だ。
全体的なお話に、あまり厚みはない感じ。
細かい部分を抜かすと、犯罪組織に潜入してその犯罪を実行する、というのが大筋になっていて、あまり大きな紆余曲折がないものだから。
ただ、大筋がシンプルであるがゆえに、枝葉の逆転逆転の話が面白く栄える。
冒頭暴走中のキットを制止しようとしてターボブーストで逃げ切られた警官が、中盤にも出てきて、キットと繰り広げるコントが笑える。
事故渋滞の迂回路を、無人カーであるキットに懇切丁寧に説明して、警官「運転には気を付けて」―キット「ええ、いつも心がけています」とまで言った・言わせたところで気付いて、他の警官に運転手の顔を見たかと聞かれたところ、「もちろん!……って、アレ?」となってしまうのが、あまりにも滑稽。
ちなみにこの警官、冒頭でも、ターボブーストに驚く他の警官の「一体何なんだあの車?」という呟きに、「ポンティアック(車種名)」とマジメにそのまま答えて、トボけた味を出している。(吹き替えではポンティアックのセリフ部分は「化け物だ」と素直な感想になっている)
マイケルが大佐の部屋に侵入する際のキットの監視モニターが、ファミコン以前のコンピューターゲーム並みの単純グラフィック(初代パックマン以下か?)で表示されていて、時代を感じさせるが、『ナイトライダー』見てた当時の我が家には、テレビゲームというかコンピューターがPC8800という、今じゃ骨董品クラスの処理能力の低いものぐらいしかなくて、それで遊んでいたのと同じようなグラフィックが映るものだから、個人的にこのシーンには親近感とちょっとした興奮を覚える(笑)
キットが外部に連絡しようと屋敷を脱出するために、門の監視施設の電子装置発火させて門番の気を逸らすのだが、目論見通り火事の消火に門番が注目してキットは脱出に成功…
…はいいとして、なかなか火が消えなくて大火事になりかけてるのに、自分で消せない火が出たら誰か他の奴に知らせろよ、門番!(笑)
★本国放送版&原語と日本放送版&吹き替えの違い
ターボブースト並みに多用される機能であるマイクロジャマー(電子装置操作電波)だが、本国放送版ではこの話で初めて搭載される新機能。
しかし、日本放送版では放送順いじってきたせいで今まで散々使ってきた機能ということになっている。
にも拘らず、マイクロジャマーを新しい機能として取り付けたという説明がそのままアフレコされている。
このシーンのボニーが、マイケルの怪我よりもキットのメンテナンスを心配していて、さっくりヒドい。
あと、キットよりもドライバーに改良の余地ありと評するトコも扱いのヒドい部類だが、マイケルも自虐的にそのセリフをハモってるから、表面上はまだマシか。
この扱いを受けてマイケルが「(ボニーの)つなぎの中身はロボットなんじゃないの?」と皮肉るのだが、キットがそれを受けて「中身はロボットじゃありませんね、身長は~」とスリーサイズ含む等々の身体データ解析を行ったところ、マイケルに止められるのだが…
日本放送版ではマイケルが「覗きはよせ」と言って、キットが「はぁーい」とおチャラけた返答するので、キットがおふざけをしたという感じになっている(ちなみにここの野島昭生の演技は、キットを抱きしめたいほどカワイイ(笑))
一方原語は、マイケルが「Shut up(黙れ)」と制してキット無言でシーンが終わるので、ここら辺のやり取りがキットのマジのボケだと分かる。
初期のキットって、いかにもコンピューターという感じの、融通の利かないやり取りとかボケが多いからなぁ~
そして、キンケード大佐の屋敷に入る際のキットの反応も、字幕と吹き替えで違う。
原語では「(マイケルがヤバくなった場合自分もヤバくなるのがヤなので)ここに駐車してはどう?」―マイケル「ダメ」―キット「やっぱり」という案外薄情なやり取りになってるが、吹き替えは「私を置き去りにはしないですよね?」―マイケル「するもんか」―キット「良かった」と絆を重視したアフレコに替えられている。
日本放送版では、デューガンがキンケードの屋敷に辿り着いて捕まるまでの一切の描写がカットされている。
キンケード大佐がどうやってどのタイミングで本物のデューガンにあったのか、本国版の方が分かりやすいといえるが、途中のデューガン逃亡のシーンは日本版でもカットされていないから結末は予想できるし、デューガン登場時の衝撃が出るから日本版でも私は好きだな。
「消えた証人を探せ!爆走ナイト2000波止場の大激突!!」
(原題“THE FINAL VERDICT”…訳すと、「最終評決」)
無実の殺人罪を着せられた友人を救うため、マイケルが友人のアリバイを証言してくれる男を探すのだが、その男・会計士マーティは、ファルコン社の裏帳簿制作の関わる事件で警察・社長一派双方から追われていた…という話。
こういう筋の話なら、マイケルは警察・社長一派を振り切って、接触困難なマーティを探し出すと同時に、友人の殺人事件の謎も追わなければならない、というハードタスクが課せられて物語は慌ただしく複雑に進行しそうなものだが、友人の殺人事件の件は、エンディング前の最終パートで「真犯人も見つかって良かった」とセリフ一言で済まされてしまう肩すかしぶり。
最初っからマーティを目指すようなシナリオしとけばいいのに、と強く思うが、ここで女性キャラ出しとかないと、この話ヒロイン居なくなっちゃうから(笑)
ヒロインいなくても、ヒロイン級にか弱いマーティの描写でこの話は結構持つけどさ。
警察・社長一派・マイケルの3勢力に追われてビクビクのマーティが哀れだ。特に後半に自宅に帰ろうとするところ。
この話で、キットとの通信機付き腕時計のコムリンクが初めて壊れる描写があるのだが、キットと連絡取れなくてマイケルたちが更なる厄介な状況に陥るのかと思いきや、キットが自己判断で動いてさしたる困難もなく状況解決するし、最終的にオチの腕相撲ネタに使われる程度だったのが拍子抜け。
ラスト5分近くは延々とカーチェイスで、坂道の多いサンフランシスコでの立体的なチェイスを堪能できる。
本国版ではこの話でキットに似顔絵機能が追加されているが、この機能も日本版では散々出てきた機能。
なので、日本語版アフレコでは、似顔絵機能の解像度がアップしたということになっている。
いや、パソコンがお亡くなりになられたというか、線がダメになってしまったと言った方が正しいか。
昨晩深夜、パソコンを使っていたら、開けた窓の方から花火の残り香が漂ってきて、「こんな遅くにどこの子が花火なんてやってるんだろう…」と思って、フとそちらの方に顔をやると…
パソコンの電源ケーブルからもくもくと白煙が上がっておりました。
「ああそうか、花火は色付きの火花出すために火薬の中に金属混ぜてるから、パソコンの金属部分も高熱で溶け出すと同じような臭いがするのだなァ」と感心を
している場合じゃない!
慌ててケーブルをコンセントとパソコンから引っこ抜いたのですが、電源ケーブルなしではバッテリーが1分と持たないポンコツPCはすぐ様ダウン…
電源ケーブルは、導線か交換機のどこかが壊れたようで、まったく電気供給しなくなってしまった…
というわけで、元のパソコンが全くもってダメになってしまったので、6年ぶりにパソコンを買い替え、Windows7搭載型の新型モデルを我が家にお迎えいたしました。
でもウチにWindows7対応の画像作成ソフトなんてないぞー
いろいろと絵を描きたいのに…
…古い電化製品にはご注意を。
 『ナイトライダー』はシリーズ途中で音楽担当者が代わっている。
『ナイトライダー』はシリーズ途中で音楽担当者が代わっている。あの印象的なテーマ音楽を作ったのがステュ・フィリップスで、11話までは彼の担当なのだが、それ以降はドン・ピークに代わっているので、これ以前と以後では、サウンドトラック音楽の印象がかなり異なる。
交代後は弦楽器やテクノサウンドで構成されたスコアが多くて、これが私個人の『ナイトライダー』音楽の印象を形作っているのだけど、交代前は管楽器中心のスコアが目立つ。
この巻は、まだ交代前なので、ステュ・フィリップス担当の音楽。後の第1シーズン後半以降の話に馴染みが深いと、音楽の雰囲気にちょっと違和感を覚えるかもしれないけど、個人的にはそれもちょっとしたバリエーションとして、楽しい。
「死の山荘脱出作戦! ナイト2000殺しのバリケード大突破!!」
(原題"JUST MY BILL"…訳すと、「これぞ我が案」)
デボンと近しい州上院議員であるマギーの命が狙われ、その護衛と事件調査にマイケルが赴くが、途中マギーがマイケルと離れて山荘へ外出中に道が封鎖され、同時にマギーが反対していたダム建設法案の強行採決が進められてしまい、マイケルはマギーを議会に呼び戻すため、封鎖された山荘へ突入する…という話。
初期エピソードらしく、キットの魅力的な部分が描かれている。
今話は、駐車禁止のところに停めても、警備員に目を付けられたらキットが勝手に移動してくれているというネタ。
地下駐車場警備員との駆け引きがサイレント映画風に繰り広げられ、コミカルで面白いシーケンスだが、日本放映版ではバッサリカットされていたな。
また、マイケルがキットに秘書のジェーンを残して出かけた際、キットが会話相手になってくれていたが、「あなたと会話するためのデータは揃っています。大学での成績はあまり良くなかったようですね」みたいなデリカシーの無い会話が如何にも融通の利かないコンピュータらしいやり取りになっていて笑える。
ただしこちらは日本放映版でもしっかり描写されている。
第2シーズン放映後、ウィットに富んだ会話ができないキットというのも何か変な感じではあるが。
「命をつなぐ水 渓谷の水を守りぬけ!」
(原題"NOT A DROP TO DRINK"...訳すと、「一滴も飲めない」)
日本未放映のエピソード。
DVD発売時に後付けで付けられた邦題なので、放映中に付けられた他の仰々しい邦題に比べて、ちょっと迫力が足りないかな(笑)
猛牛vsキットの興味深い対決あり、スキーモードをバックで起動させて建設用機械の攻撃から逃れるアクロバットあり、迫力の爆破シーンあり、キットが宇宙人の振りをして敵を追い詰めるコメディパートあり、親と子のドラマあり、と魅力的で盛りだくさんな内容なので、未放映になっているのが惜しいほど。
第3シーズンの「爆走デビル・トラック!必殺クラッシュ!巨大タイヤの恐怖」が同じく牧場が舞台の話なので、似たようなのは避けたのかな?
ナイト財団の正式名称が「法と政府のためのウィルトン・ナイト記念財団」であることを頭に入れておくと、冒頭、マイケル無しでデボンたちが訴訟問題に立ち会っている違和感が解消されるかもしれない。
あくまで弁護士派遣とかの法律関係の仕事や公的機関の補助の事務を行うのがナイト財団のメインの仕事で、マイケルたち実働隊(いわゆるF.L.A.G.)は強行手段でやってくる相手に対する対処部署なのだと。
この話の中では、夜間は自動操縦でキットに運転させてマイケルは仮眠を取る、という、もし自分がキットを持っていたら是非実践してみたい理想的・実用的な使い方をしている。
まだまだキット魅力宣伝時期であるのだなぁ
「デボン逮捕!決死の脱獄 迫る巨大トレーラー!橋上の対決」(原題"NO BIG THING"...訳すと、「大したことはない」)
キットのガス欠についての「ボニーが入れ忘れたんだな」「あなたのナンパドライブはボニーの計算には入っていませんよ」辺りのやり取りは、日本放映版でもちゃんと吹き替えがあるのに、このDVDではその部分がごっそり削られている。
日本側で独自の編集をしていて映像と吹き替えがきっちりとは合わないようなのだが、この後の話でも箇所によってはそういう勿体ない部分があるようだ。
デボンが逮捕されてしまうという衝撃の展開。
日本放映版では、開始後20回近く経ってからの放映だったので、よくあるキャラ掘り下げ回のようでもあったのだが、本国ではこの早い時期に放送されていた、デボンの担当回。
マイケルの活躍部分はそれほど多くなく、デボン解放に至る部分で最後らへんしか貢献できていない。
逆にデボンの行動が話を引っ張っていて、刑務所からの脱獄にやたら思い切りが良く張り切って暴れまわるのが、デボンとしては“らしくない”感じがして、だからこそ面白いなぁ~
この話でキットは、バック走行でトラックの追跡を振り切る。
この直前のセリフは、マイケルが町の実情を聞いて、吹き替えでは「正直信じられないな」「3日も居れば嫌と言うほど分かるわ」となっているけど、原語では「随分ひどいことがあったんだな」「3日も居れば精神がおかしくなるほどよ」となっていて、マイケルの理解が全然違っていることになっている。
当時の日本人には、警官がはっきりと悪意を持って市民を陥れているっていうのは、フィクションの世界でもありえなさすぎる・ひどすぎるという考えがあると思って、マイケルがすんなり信じるのは日本人的には変だろうという判断からの改変だろうか…?



月給2万の低給に感動し、チャイナ服のスリットにやたらこだわる緒花の貞操観念が心配です(笑)
第七話「喜翆戦線異状なし」



ヤケにギャグのキレがいいなぁ~と、思っていたら、絵コンテが岡本天斎だった。
第十話「微熱」



風邪ひいてる時、テレビ点けたがる菜子の心境はよーく分かる(笑)
第十一話「夜に吼える」



1クール目終了に向けてのダッシュ回
その前2話で絵コンテだけ担当していた篠原俊哉が、今回は監督のコンテで演出担当している不思議。スタッフローテション、どうなってるんだろうと、このアニメに限らないけど、思う。
第十三話「四十万の女~傷心MIX~」



今のところ一番好きな話だなぁ ちょっと重い話が続いた後の解放回だからというのもあるだろうけど。
お互いに相手を他人と思わなくてはならない仕事上の関係でありながらも、女三世代が久々にというか初めて揃って腹を割って酒を酌み交わすというシチュが微笑ましくって仕方がない。
孝ちゃんに未練があるんだけど目の前の仕事に影響するので断ち切らなくては…という流れが途中にあって、分けてシナリオを進めそうなところの“緒花の仕事の話”と“恋の話”を同時的に処理していて、上手いなぁ~と思ったけど、この程度は実写ドラマ・映画では日常茶飯事か。
第十四話「これが私の生きる道」



OP、ED変更。OPは より動きが激しくなった。でも、孝ちゃんが映るシーンだけなんか重いよ(笑)
あと、最後喜翆荘のみんながOPの最後で明日の方向むいて勢揃いしてるってのが一昔前の異世界冒険ファンタジーモノのOPの最後の絵みたいで、懐かしい感じが…(笑)
それ、旅館モノのアニメのOPの締めに合ってないから! 全員集合写真なら、せめてお客(視聴者)を迎えるような感じの画でですね………って、それだと構図が平板になるな。
ようやっと結奈回。この作品のキービジュアルには出てくるのに本編での出番がイマイチなかったり、フワフワした感じのギャル系の性格に見える割に裏が見えなくてキャラを掴みきれない結奈だったので。
「いろいろやりたいやってみて、一番やりたいことを仕事にするの。でもやりたいことの中に旅館の仕事は入ってないの。これが私の答え。」という最後のセリフでようやく裏というかキャラ造形の深みが見えた。うん、やりたくないものは手を付けないって、スゴく今どきの子!
一方で、修学旅行中も大手旅館の偵察を欠かさない緒花は、どんどんキャラ描写が単純になっていっているよーな(汗)
 『タイバニ』に続く、サンライズ原作のヒーローモノ、第2弾か?
『タイバニ』に続く、サンライズ原作のヒーローモノ、第2弾か?『タイバニ』もレトロ感覚の強い作品ではあるけれど、コイツはコイツで別の意味で、何だか古臭い印象を受けるアニメだなぁ…
主人公の変身後の姿が、個人的に聖闘士星矢を連想させて仕方ないというのが理由(笑)だが、一般人を容赦なく殺していく敵とかそれを特に気にしないシナリオ展開とかは昭和ライダーみたいだし、お金持ちの私有軍がバリバリ前線に出てくるところが80~90年代のアニメっぽいし、何より、”変身”って単語が主人公に似合う時点で今風の設定じゃあない。
とは言っても、キャラデザが千羽由利子・中谷誠治という『コードギアス』布陣だったり、ヘリの操縦から狙撃部隊まで対応可能の有能メイド隊が出てきたり、売れ線意識してる作りではあるが。
ただ、おかげで私には結構合うかも。
大きい理由は、前回のラストバトルが巨大化した敵、今回が云百キロメートル級の雲海を隠れ蓑にして飛んでくる巨大浮遊物体との戦いと、怪獣映画さながらの描写が心地よくってねぇ~、ってところなんですけど(笑)
今作監督の大橋誉志光は、私が視聴済のものでは、『ウィッチブレイド』・『幕末機関説 いろはにほへと』と、設定とか話の流れとかは面白くてワクワクするものが多いのだけど、最終的にはイマイチ突き抜けてくれなかった作品が多いので、なんかコレもそんな臭いがしつつ、他の作品同様キライにはなれないのかなぁ、と。
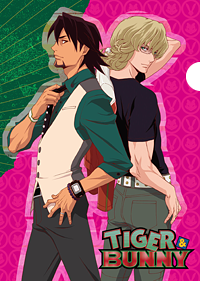 「ビッグオー、ショータイム!」
「ビッグオー、ショータイム!」
いや、『ビッグオー』見てた人なら、今回のキャスティングで絶対連想するでしょ
感情希薄なアンドロイド少女@矢島晶子とその保護者的な男性@宮本充って組み合わせでの配役。
愛した人をそれと知らずに殺してしまう、という『TIGER&BUNNY』初の鬱オチ。
報われないスカイハイだが、知らぬが仏、という形のハッピーエンドではあったのかな…
愛といっても、アンドロイド少女にはキャラクター性皆無なのに、スカイハイが入れ込んでたというか一方的な思い込みだったという描写のようになっているのも、その深く鬱ではない印象に繋がってるかも。
前回は、バーナビーが虎徹べったりで気持ち悪いほどだったが、今回は虎徹を慕っているけど欠点も理解してるって苦言も呈する感じのほどよい距離になってた気がする。
前のスペシャルの感想で、「これを『名探偵コナン』を実写で再現するドラマだと思ってはならない、設定だけを借りた新種の推理ドラマと考えるべき」というようなことを書いたけど、そこらへんはシリーズになっても変わっていない。
相も変わらずネームバリューだけで、雰囲気誤魔化している感じだが、私みたいな「特に見たいわけではないけど、『コナン』だし、何か推理モノを軽ぅーく観てみたいな」なんてあまりマジメでない思いで観るヤツもいるわけで、私もしっかり釣られている以上、ネームバリューもバカにはできん(汗)
『CUBE』みたいな部屋に囚われた新一・蘭・小五郎が、部屋から脱出するパスワードを探るために、過去の事件を思い起こしていって、それがその回のメインの話になる、という、よー分からん連ドラ仕掛けが施されている。
『コナン』本編との整合性を取ろうという気はないようで、新一がコナンになる前の話なのに、佐藤刑事と新一に既に面識があったりする。高木刑事はいつ知り合ったんだか分からんから良いとして(笑)(あっ、新一の高校生探偵デビューのニューヨーク行き国際線機内の事件ですでに会ってるか)、佐藤刑事はコナンになった後知り合ってるし、新一として会話したのは原作68巻になって初めて会ったぐらいだから。
この分だと平次も出てきそうだが、ヤツも新一がコナンになった後の知り合いである。
…でも、こーでもしないと、少なくとも原作のキャラクター的な旨みが発揮できんしなー。
高木刑事から「彼は高校生探偵なんです、だから今回の捜査に協力をしてもらってます」なんてセリフが出てきたり、「推理が違っていた場合は、探偵を廃業します」と新一が宣言したり、どんだけ探偵の概念と権限が肥大化してるんだ、この世界…と思ってしまった(汗)
そら、原作でも小五郎が“名探偵”という理由だけで捜査に参加してたりするが、アレでいて警察に顔が利く元刑事だし、ちゃんと素行調査とかで稼いでるプロだし、少なくとも推理だけしかしない高校生が探偵開業してるのより説明つけられたりするんだぞぉ~
最近オリジナルアニメが盛況との話ですが、それは売れているアニメにオリジナルモノが多いということであって、オタク全体の購買力のキャパが限られてる分、その影響を食らって売上的には不調な作品もあるだろう。
なんかこれもそっち側になりそうな雰囲気が…
Production I.G.がCLAMPを召喚して、水樹奈々主演で水島努監督に作らせた、『BLOOD』シリーズの新作。
ヒットメーカーを呼んできて、売れ線狙っている感じだが、企画の段階でいまいちピント外している気がせんではない…
前作『BLOOD+』がさほど振るわなかったのに、なぜに今になって『BLOOD』なの?…と思ったりしたが、I.G.でよく知られたオリジナルがそれぐらいしかないからなのかな…
OPディレクター:梅津泰臣とクレジットされたところで、なぜか笑ってしまった。顔が全然梅津キャラっぽくないなーと思ったら、作画監督は別に立ててた。
『BLOOD THE LAST VAMPIRE』で強烈な魅力だったのに、『BLOOD+』で削ぎ落とされていた、“制服着た女の子が日本刀持って吸血鬼退治”というアンビバレンスな要素が今作ではしっかり復活。
なぜか襟の部分にチェーン付いてる制服の構造というか、コンセプトは謎だがな(笑)
その代わり、小夜のバックに全容の知れぬ対怪物組織が付きながら敵と対決していくという外部に広がる設定はなくなり、人知れず血みどろで妖怪退治という内向きのバックボーンになって、全然違う話に。
『BLOOD』シリーズというより、主人公の髪型とか見てても分かるけど、実にCLAMP的だなぁーと。
主人公の小夜も、『~THE LAST VAMPIRE』の狂気染みたストイックな子、『~+』の割と普通な女子高生という流れから大きく変わって、よく転ぶドジっ子属性追加。…あ、阿漕になってやがる。
「生存、戦略ぅぅー!」
 最近はハードディスク録画機の番組表だけ見て、アニメとか録画しているのでロクに注目もしてなかったのだけど、ネット上で「生存戦略ー!」「このセンスすげぇ!」「途中から別の作品になったぞ!」とか大反響になっているので確認してみたら…
最近はハードディスク録画機の番組表だけ見て、アニメとか録画しているのでロクに注目もしてなかったのだけど、ネット上で「生存戦略ー!」「このセンスすげぇ!」「途中から別の作品になったぞ!」とか大反響になっているので確認してみたら…
…元々東映で『セーラームーン』とかを担当していたけど、その頃から独特のセンスを発揮し、独立後『少女革命ウテナ』でアニメ回に衝撃を与えた幾原邦彦監督、12年ぶりの新作アニメだった。
…でもすみません、私、『ウテナ』観てません…(汗)
おまけに、途中ワイプの代わりに電車の電光表示板風の演出が差し込まれたり同ポジ・リフレイン演出が出てきた辺りで、細田守っぽい、とか思っちゃう始末。
細田守は幾原邦彦監督の『ウテナ』の下で絵コンテ・演出やってたんだから、影響の矢印は逆だよ、オレ…
「実に幾原監督っぽい作品だ」という評が多いけど、実際どの程度幾原監督のセンスや意向が寄与しているのかな。
この作品、監督の下(?)にシリーズディレクター・中村章子が配置されているし、脚本家もあまりこちら系ではない人を引っ張ってるみたいだから、そちらの影響というのも反映されている部分、あるかもしれんし。
(書きかけ)
原画
林明美/馬場充子/井野真理恵/進藤優/益山亮司/後藤圭二/佐藤雅将/加々美高浩/薗部あい子/中村深雪/いとうまりこ/古川知宏/すしお/肥塚正史/中村章子
スペシャルアニメーション(クリスタル・ワールド)
原画
細田直人/林明美/杉本功/後藤圭二/長谷川眞也/光田史亮/進藤優/馬場充子/柴田勝紀
オープニングアニメーション
絵コンテ:幾原邦彦・古川知宏
演出:幾原邦彦
作画監督:西位輝実・柴田勝紀
原画
相澤昌弘/馬越嘉彦/後藤圭二/柴田由香/進藤優/長谷川眞也/柴田勝紀/武内宣之/中村章子/西垣庄子/馬場充子/林明美
1st station
「運命のベルが鳴る」
絵コンテ:幾原邦彦 演出:中村章子 作画監督:西位輝実










